子どもが「学校に行きたくない」と言った時の初動対応マニュアル
子どもが「学校に行きたくない」と言った時、どのように対応するのが良いのでしょうか?実は最初の行動が重要となります。
心を落ち着け、子どもの気持ちを受け止める
子どもが「学校に行きたくない」と告げた際、まずは保護者自身が心を落ち着けることで、冷静に対応できる状況を作り出せます。落ち着いた雰囲気を作ることによって、子どもが安心して悩みや不安を伝えやすい環境になるのです。
例として、保護者が大きな声で感情的に反応しないようにし、静かに「今どう感じているのか」尋ねる方法が挙げられます。保護者が平常心を保ち、無理に理由を聞き出さず見守ることで、子どもから本音を話してもらえる可能性が高まります。
今日の方針を決定
初動の段階で家庭内での方針を決めておくことで、子どもへ分かりやすい安心感を与えられます。「今日は休もう」「無理に登校しなくて良い」など具体的な選択肢を子どもに伝えることで、子どもの精神的負担を軽減しやすくなるのです。
例えば、午前中は家で一緒に過ごし午後から考えるという時間割を用意すると、次の行動が見えやすくなります。家庭内ルールを明確化し、その場しのぎの対応を避けることで、子どもの混乱を抑制できます。
学校連絡と当日の過ごし方を決める
家庭での判断が終わった後は、速やかに学校へ状況を連絡することが信頼関係の維持のためにも必要です。連絡では、子どもの同意を得たうえで現状の心身の様子と保護者の見解を簡潔に伝えます。
当日は生活リズム維持を重視し、リビングで過ごす時間の組み立てや学習・遊びのバランスを事前に決めておくケースが効果的です。学校側と連携し、無理に復帰を急がない意識を伝えることで、家庭と学校双方のストレスを軽減できます。
学校に行きたくない理由を聞く前にやるべき初動対応
次に学校に行きたくない理由を聞く前にするべき初期対応を3つ紹介します。
- 感謝の気持を伝える
- 「休んでもいい」という安心感を言葉で示す
- 体調面の確認と心の状態把握を最優先で行う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
感謝の気持ちを伝える
子どもが学校に行きたくない意思を伝えてきた際は「言ってくれてありがとう」と、気持ちに感謝することが信頼関係の基盤を作ります。理由を聞き出す前に勇気を持って相談した事実そのものを認めると、子どもは否定されたという感情を持ちにくくなるのです。
例えば、「よく話してくれたね」と本人の目をしっかり見て言葉を掛ける方法が有効です。 最初に感謝を伝えることで、その後のやり取りで子どもが本音を出しやすい状態を作れます。
「休んでもいい」という安心感を言葉で示す
初動の対応で「休んでも問題ない」と明言することで、子どもの精神的な緊張を和らげる効果があります。「行きたくない」と話せた子どもは強い不安やストレスを感じているため、本人の選択を認める言葉が大切です。
実際に「今日は何もせず休もう」「無理に学校へ行かなくて良いよ」と伝えるケースが安心材料になります。こうした声かけによって、子どもの心が落ち着き、徐々に次の行動に向けて前向きな選択がしやすくなります。
体調面の確認と心の状態把握を最優先で行う
子どもが学校を嫌がった場合は、発熱や腹痛などの身体的な変化が隠れている可能性もあるため、身体の様子を必ず確認します。また、落ち込みや無気力、食欲不振といった精神的なサインが現れていないかも併せてチェックする必要があります。
具体例として、検温や症状の聞き取りに加えて、「気分はどう?」と穏やかに尋ねる方法が基本です。身体と心の両面を丁寧に確認することで、本人の深刻な不調を見逃さず、適切な対応につなげられます。
子どもが「学校に行きたくない」と言った当日の過ごし方
子どもが「学校に行きたくない」と言った当日の過ごし方にもポイントがあります。ここでは以下の観点をもとに当日の過ごし方についてお伝えします。
- 午前中は生活リズムを維持し普段通りに起床・朝食
- 昼間はリビングで過ごし、寝室に引きこもらせない
- ゲーム・動画時間の制限ルールを設定
- 午後に気持ちの整理時間を設け、一緒に解決策を考える
- 夜に翌日の準備と不安軽減の声かけを行う
それぞれ詳しく解説します。
午前中は生活リズムを維持し普段通りに起床・朝食
朝、決まった時間に起きて家族と一緒に朝食をとることで、心身ともに安定した一日を始められます。規則正しい起床と食事は体調管理に役立ち、長期的な休養や健康への悪影響を予防できます。
親子で天気やテレビの話題で会話しながら朝食を囲むと、安心できる家庭環境が作れるのです。平日の登校が難しい場合も、朝のルーティン維持は学校への復帰や本人の自己管理力向上に寄与します。
昼間はリビングで過ごし、寝室に引きこもらせない
家族の視線が届くリビングで過ごすことで、孤独感や社会的な疎外を避けて精神面の安定を保てます。寝室など閉鎖的な空間に長時間いると気持ちがふさぎ込みやすく、生活も乱れがちです。
例えば親子でボードゲームや雑談を楽しみ、家事の手伝いなどできる活動を一緒に実行すると良いです。開かれた居場所づくりで、本人が受け身でなく能動的な行動へ移れる土台が整います。
ゲーム・動画時間の制限ルールを設定
電子メディアは誘惑が大きいので、具体的な利用時間を決めることで生活リズムを維持できます。無制限の利用は夜更かしや睡眠不足を引き起こし、心身の不調を招きやすいデメリットがあります。
たとえば、「午前一時間」「午後一時間」と家庭で合意したルールを設け、張り紙で明示すると効果的です。家族で約束を確認し合うことで、本人自身が自制力を高め生活習慣の安定につながります。
午後に気持ちの整理時間を設け、一緒に解決策を考える
昼食後にゆったりした時間をとり、親子で現状や不安について一度言葉にして確認することが大切です。本人が自分で問題の原因や気持ちを整理できると、前向きな考えや行動への意欲が生まれやすくなります。
たとえば「できることを一つ決めてやってみる」など小さな成功体験を親子で持つ工夫が大切です。和やかな対話を心がけると、本人の希望や現実的な目標を具体化しやすくなります。
夜に翌日の準備と不安軽減の声かけを行う
夜は翌日の予定や持ち物を一緒に確認し、本人の不安に配慮したやさしい励ましが大切です。準備が整うと翌朝の混乱を防ぎ、安心して一日を始める体制が整います。
「何時に起きようか」「必要なものはそろった?」と具体的に問いかけることで安心材料を増やせます。見通しを持って声を掛けることで、本人が主体的に準備と行動に取り組みやすい環境が作られます。
初動対応で絶対にやってはいけないNG行動6選
ここでは、初動対応で絶対にやってはいけないNG行動を6選を紹介します。焦るとやってしまいがちな内容でもありますので、注意しましょう。
叱責や感情的な反応を示すこと
親が怒りや否定的な態度で接すると、本人の気持ちが萎縮し本音を話しづらくなります。強い言葉が続くと自己肯定感を傷つけ、相談の機会が減り問題解決から遠のいてしまうのです。
例えば「そんな弱い子じゃ困る」と叱ると、恐怖心や自信喪失につながる危険性があります。冷静な対応や肯定的な声かけをすることで、悩みの打ち明けや回復の意思を引き出しやすくなります。
「どうして行けないの?」と理由を詰問すること
親が理由の説明を繰り返し求めると、答えられないことに強い罪悪感や焦りが生まれます。子どもは感情を言語化するのが難しいケースが多く、詰問型の質問では心が閉じてしまう可能性があります。
例えば「言いたくないならいいよ」と気持ちに寄り添い、本人から自然に言葉が出るタイミングを待ちましょう。 積極的な共感姿勢が本人の安心感を育て、本音の対話や悩みの整理に役立ちます。
無理やり学校に連れて行くこと
物理的な登校強制は強い不安や恐怖を抱かせ、学校自体の拒否につながるケースがあります。急かして校門まで連れて行くなどの行動では、家族への信頼感や相談力が低下しやすいです。
玄関で「今すぐ行こう」と無理に促す代わりに、一緒に家で過ごす提案や短時間の外出してみることをおすすめします。本人の意思を尊重し、タイミングを見極めることが、長期の不登校や精神的な後遺症を防ぐ一歩となります。
「そんなことで休むの?」と軽視すること
相談を軽く扱う態度は本人の自己評価を下げ、孤独感や悩みの長期化の原因となります。「他の子は頑張っているのに」と一般化した比較を使うと、理解してもらえない疎外感を感じやすいです。
悩みが小さいと思われる内容でも、本人にとって深刻な場合が多く、丁寧な対応が不可欠です。共感のある声かけと受け止める姿勢を意識すると、安心感を与え、今後の相談に前向きになれます。
他の子と比較する発言をすること
兄弟や同級生との比較を含む発言は、自己価値を大きく損ない、対人関係への不安も高まります。「妹は頑張っている」と強調する対応では、本人が自分自身を否定しやすく精神的負担が大きいです。
本人独自の努力や目標を認める工夫が、回復や再登校への自信獲得につながります。相対評価ではなく個々の歩みを応援すると、自己肯定感や問題解決能力が強まりやすいです。
登校復帰だけを最優先に考えること
学校に戻すこと自体を目的化すると、本人への精神的重圧が強くなり問題が悪化します。出席日数などの形式的な指標だけを重視すると、モチベーションが下がり、学校へ行きづらくなります。
たとえば「毎日学校へ行かないと危険」と過度に急かすと、登校困難や再拒否を誘発しやすいです。最優先事項は安全な学びの場と本人の安心設計であり、焦りすぎず、子どものペースに合わせる姿勢が大切です。
子どもが「学校に行きたくない」状況を学校に伝える初動対応のポイント
子どもが「学校に行きたくない」状況を学校に伝える際にも、大切なポイントがあります。ここでは以下の4点に絞ってご紹介します。
- 子どもの同意なしに教師の家庭訪問を要請しない
- 状況説明は客観的事実のみを簡潔に伝える
- 学校側の対応方針を確認し連携体制を構築する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
子どもの同意なしに教師の家庭訪問を要請しない
子どもの同意を得ない家庭訪問は家族内での緊張感や本人への心理的ストレスを増加させる心配があります。訪問による負担が強くなると、家自体が安心できる場所ではなくなるリスクも。
本人に意向や体調を聞いて「先生が来てもいい?」と確認し同意が得られた場合だけ訪問を依頼する必要が出ます。主体的な意思を尊重する対応が子どもの安心感を確保し、家族と学校の信頼関係を築く要素になります。
状況説明は客観的事実のみを簡潔に伝える
学校への連絡では主観入れず、子どもの現状や家庭の対応を具体的に整理して簡潔に伝える必要があります。「何時頃から体調不良が見られる」「朝になると腹痛が続く」など事実をまとめることで誤解が生まれにくくなります。
過度な主観や感情的な表現は避け、「現在自宅療養中」「医師の診断を受けた」など淡々とした記述が望ましいです。正確な状況報告により学校内での対応策や必要な支援が明確になり、公平なフォロー体制を構築しやすくなります。
学校側の対応方針を確認し連携体制を構築する
学校との連携体制は、初期の方針確認や今後のスケジュール調整に役立ち、家庭での支援も一貫性を保ちやすくなります。例えば登校目的や保健室利用の可否、新たな取り組みについて事前に話を聞くと、児童本人の負担が減らせるでしょう。
双方で課題やゴールを明確化し、定期的な情報交換を継続することで、混乱や誤解が回避できます。連携を重視することで、家庭・学校・専門機関とも調和ある支援を進めやすいです。
初動対応を実践後の継続的なフォロー方法
子どもが再度「学校に行きたくない」と言う可能性も否めません。そのため、初動対応を実践後も継続的なフォローが重要となります。
毎日の心の状態チェックと記録をつける
心の状態を日々記録することで、不安やストレスの変動を具体的に把握し、早期の問題発見につなげられます。一例として、日記や相談ノートに「朝の気分」「夜の睡眠」「会話した内容」を残す方法があります。
家庭内で変化に気付いた時、すぐ学校や専門機関と連絡でき、適切な助言や支援が速やかに受けられるためおすすめです。継続的な観察を行い、長期的なメンタルケアと再発防止策を組み立てる基礎が作れます。
部分登校(保健室・遅刻・早退)の選択肢の検討
子どもの状況に合わせて保健室だけの利用や遅刻、早退など柔軟な登校パターンを確保すると負担を抑えられます。全日登校だけにこだわらず、保健室や図書室活用など安全領域から始める方法があり子ども本人の安心感を守ります。
例えば朝のみ登校して昼食後に下校する提案や、週数回だけ出席する選択肢を学校と相談することも可能です。無理のないペース調整と段階的な目標設定で、学校生活への復帰の意欲を育てやすい仕組みが作られるでしょう。
専門機関(スクールカウンセラー等)との連携準備
専門家への連携は、不登校の原因や本人の悩みの多様性に適応した専門的なケアを実現するために不可欠です。スクールカウンセラーは学校内外での調整や心理的支援を担い、相談事例ごとに個別に対応可能です。
家庭が相談を希望する場合は、事前に予約や希望日時を伝えると効率良くサポートが受けられます。関係機関へのアクセス体制を確保しておくことで、学校だけでは対応しきれない課題にもら、速やかに対処できます。
家庭内ルールの定期的な見直しと調整
家庭で決めたルールは、本人の状況や気持ちの変化に合わせて定期的に確認と変更を行うことで、ストレスを減らせます。例えばゲーム・学習・親子の会話時間などを見直し、無理なく実行できる内容に更新し続ける工夫が必要です。
保護者間でルール緩和や厳格化の検討を積極的に行うと、本人も自分のペースに合った生活へ調整しやすくなります。家庭全体の合意を得て柔軟に対応する姿勢が、長期的な精神的安定と回復に影響します。
長期化防止のための段階的な目標設定
学校復帰や日常生活の安定のためには、小さな目標を積み重ねながら段階的に負担を減らす戦略が有効です。例えば週一回の登校、オンライン学習の活用、午後だけ参加など現実的で達成できるゴールを設定します。
本人が少しずつ目標をクリアする経験を積むことで自信がつき、長期化や再発のリスクを抑制できます。過度なプレッシャーを生まず細かな行動計画を紙に書いて可視化すると、進捗管理とモチベーション維持がしやすいです。
年齢別子どもが「学校に行きたくない」時の初動対応
「学校に行きたくない」時の初動対応は年齢によっても異なります。ここでは「小学生」「中学生」「高校生」に分けて対応を紹介します。
小学生の場合
小学生への対応は家族と離れることへの不安や集団生活への慣れの遅れを前提に、安心できる家庭環境の維持に重点を置きます。保護者が日々のコミュニケーションを増やすと、潜在的な不安感や寂しさが表面化しやすくなります。
たとえば朝の身支度を一緒に進めたり「いつも見守っているよ」という言葉をかけることで、安心感が生まれるのです。 本人の表情や行動を観察し、不安な点を言語化できるよう手助けすることで学校復帰の意欲を回復できます。
中学生の場合
中学生への対応は思春期の自立心や反抗期、人間関係トラブルなど多様な課題に寄り添う姿勢が大切です。環境の変化や進路の悩み、学業や部活動のストレスが不登校の要因になるため、家庭での自由度や会話の工夫が求められます。
たとえば「相談したいときはいつでも話していい」と伝えたり、LINEやメモなど非対面の形を使う方法があります。本人が自分自身で課題解決に挑戦できるよう、幅広い選択肢とフォロー体制を用意すると自己決定力が育つでしょう。
高校生の場合
高校生への対応は進路選択や自分らしさの探求、将来への不安など、個性を重視したサポートが必要です。学業・生活の自己管理や進学・就職への悩みが背景にある場合、保護者は決めつけず意思を尊重した面談形式の対応が適切です。
実例として「いつ何をどうしたいか」本人に計画を立ててもらい、週ごと、月ごとの目標に落とし込む支援を行います。卒業後を意識しながら、進路や選択肢を広げる情報収集や専門機関相談を活用して、伴走する手法が役立ちます。
年齢に応じた言葉選びと対話方法の調整
年齢ごとに言葉や伝え方を変えると、本人の心理的負担を小さくできます。低学年にはやさしい言葉や絵カードなどの視覚的支援、中高生には事例や具体的選択肢を用いた話し合いが有効です。
「つらい気持ちを何でも話してね」と伝えたり、「どの方法なら楽になれそう?」と主体性を促す言い方を工夫します。対話の形式や内容を本人に合わせて変えることで納得感が生まれ、意思表明や悩み相談が円滑に進みます。
初動対応マニュアルを活用した親の心構えと準備
「学校に行きたくない」と思っている子どもが、年々増加傾向にあります。我が子は大丈夫とは言えないため、事前の心構えと準備をしておくことが大切です。
冷静さを保つための事前メンタル準備
保護者自身が感情に左右されず落ち着いた対応をするためには、事前の心の準備やストレスマネジメントが重要です。深呼吸や日記記録、相談機関への定期連絡を取り入れることで家庭内衝突や感情的な対応を大幅に減らせます。
たとえば毎日数分でも呼吸を整えてから子どもと接する時間を設けるなど、習慣化しておくと良いです。外部相談や心理的休憩の確保を工夫し、想定外の事態にも冷静に判断できる土台を作れます。
仕事調整や家庭環境整備の準備
保護者が職場や家庭のスケジュールを柔軟に調整し、余裕のある対応できる体制を事前に用意しておくことも大切です。有給休暇の取得申請や在宅勤務への切り替えを検討しておきましょう。
近隣サポートの調整を行うなどすることで、急な呼び出しや家庭内対応に備えられます。 家庭外を活用しながら、家族の精神的ゆとりや安心感を高める環境づくりもポイントです。
緊急連絡先リストと相談機関情報の整理
万が一に備えて学校・専門機関・地域支援など、関係先の連絡先と対応マニュアルを整理しておくことも重要です。携帯電話や手帳など必ず確認できる場所に記載しておきましょう。
学校、自治体、医療機関などの連絡先リストは家族全員が見られる場所に置いておくことをおすすめします。 情報をまとめておくことで、緊急時の混乱や情報不足を防ぎ、適切な相談・連携支援が迅速にできます。
家族間での対応方針統一と役割分担
家族全体で対応方針を事前に話し合い、担当者や連携のルールを決めておくことで混乱や連絡の漏れを未然に防止できます。例えば親同士で日々の対応担当を分けたり、子どもとの会話担当者を明確化するなど具体的な調整が必要です。
方針をまとめるには定期的な家族会議や進捗共有が大切で、思い違いや誤解の予防にも役立ちます。方針と分担を明確にすることで、困難な場面でも冷静な判断をしやすく、継続的なサポートも可能です。
長期戦に備えた体制づくりと心の準備
不登校対応は短期間で解決できない場合が多く、家族が長期的に支えていく覚悟と準備が不可欠です。日々の予定表や個別目標を作り、数週間単位で進捗を持続的に確認する習慣が、精神面の支えとなります。
例えば、家族それぞれが息抜きの時間や定期的な相談先を持つことで、心身の負担を分散できます。長期的なフォロー体制と継続的な意識共有を通じて、困難な状況でも諦めずサポートできる環境が整うでしょう。
まとめ
子どもが学校に行きたくないと言うことがあれば、焦らず本人の気持ちと状況の把握を丁寧に行うことが重要です。家庭と学校が協力し、柔軟で段階的な対応を積み重ねていくことで、子どもも安心できる生活環境を築くことができます。
本人のペースに合わせて小さな目標設定や支援先の活用も選択肢に含め、多様な気持ちを尊重してください。学校復帰だけを目的にせず、日々の心のケアと、家庭の穏やかな関係づくりを重点的に取り組む姿勢が大切です。
ぜひ本記事を参考にしつつ、子どもと向き合えるよう意識しましょう。
【参考資料】
長野県教育委員会(2025)「不登校児童生徒支援の手引き~子どもたちの社会的な自立を支援するために~」 https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/shido/documents/r7hutokotebiki.pdf
菅原ますみ・北村俊則・戸田須恵子他(1999)「不登校発生の背景要因に関する研究」『家族心理学研究』31巻1号 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jafp/31/1/31_43/_pdf/-char/ja
佐藤主馬(2023)「不登校に関する研究の主題とその動向」『青年心理学研究』47巻1号, pp.13-24 https://www.jstage.jst.go.jp/article/adsj/47/1/47_13/_article/-char/ja/
福岡県教育委員会(2024)「福岡県不登校児童生徒支援リーフレット」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/778589_62557689_misc.pdf
千葉県総合教育センター(2024)「不登校生徒の支援に向けた校内体制の充実のために」 https://cms2.chiba-c.ed.jp/kosapo/cabinets/cabinet_files/download/48/cbc90d4118965c47488c991cea74ee99?frame_id=75
公益社団法人子どもの発達科学研究所・浜松医科大学子どものこころの発達研究センター(2024)「不登校の要因分析に関する調査研究報告書」
https://www.mext.go.jp/content/20240322-mxt_jidou02-000028870_02.pdf


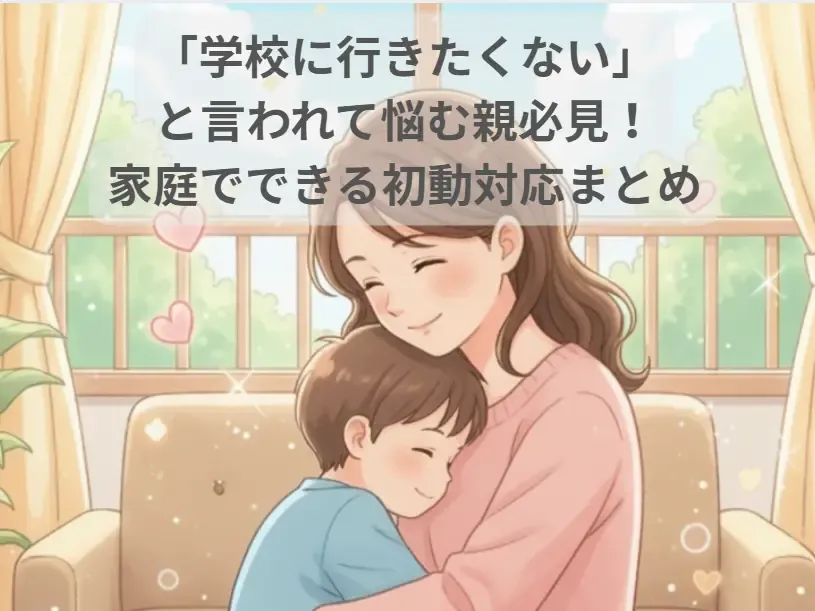
%20(1)-2.webp)