不登校は誰にでも起こりうること
「不登校」は「風邪」に似ているかもしれません。
なるべくなら、いつも元気に笑って活動していたいけれど、何かのきっかけで風邪をひいてしまうことは誰にでもあるものです。
登校もこれに似ていて、きっかけはお子さん自身も言葉にはできないけれど、ちょっと心が重くなったり、学校での場面が繰り返し頭に浮かんだりしているうちに、どうしても学校に行くのがいやになってしまう。
風邪をひくのが特別なことではないように、学校に行けない・行かないという気持ちになるのも特別なことではありません。風邪をひいたら、ゆっくり休まなくてはいけないように、学校に行きたくなくなったらゆっくり休んでいいのです。自分の心と体を大切にすることは、とても大切なことですから。
日本では平成28年に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が公布され、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる環境を確保すること、不登校児童生徒への個別の状況に応じた支援を行うこと、そして、義務教育を十分に受けていない者の意思を尊重し、能力に応じた教育機会を確保することは国の義務である、ということになりました。
それに伴い、自分の気持ちに素直に従って学校を休むという選択をする子ども達が増えています。
では、実際にわが子が不登校状態になった時に、保護者はどうすればいいのでしょうか?
不登校?と感じた時の初期対応
◎子どもの気持ちを否定しない
わが子に「学校に行きたくない」と言われたら、どんな親でもドキッとするはずです。
でも、「学校に行きたくない」と伝えることも、お子さんにとっては勇気が必要だったのではないでしょうか。
まずはその勇気を認め、お子さんの気持ちを否定せずに受け止めてあげることができたなら、最初の対応は大成功です。
◎無理に理由を聞き出そうとしない
お子さんの気持ちを受け止めた後、「どうして休みたいの?」「何かあったの?」と続けて聞きたくなる気持ちはよくわかります。でも、ここはぐっとこらえて、原因探しは後回しにしましょう。
冒頭でお伝えしたとおり、お子さんは今、心が風邪をひいてしまった状態です。辛い時は、原因探しよりもまず安静を優先しましょう。心と体が十分に安心感を得ることができたなら、何があったかはお子さんが自然に話してくれるようになるかもしれません。
親も子どもも、心を元気にしよう
◎保護者が心身のバランスを崩さないように
ここまで保護者がするべき初期対応について書いてきましたが、理由を聞きたい気持ちを我慢したり、不安な気持ちを抱えたままでいると、今度は保護者の方が辛くなってしまいます。
落ち着いて子どもの話を聞くためには、保護者の側にも十分な気持ちの余裕が必要です。子育てはもちろん、仕事や地域の活動などでも忙しくしている保護者にとって、心と体の状態をよいバランスに保つことは何よりも大切です。
◎休む・相談する・頼ることも大切
そのためにも、「ちょっと疲れたな」「私も辛くなってきた」と感じた時には、無理をせずに休んだり頼ったりすることを積極的にしてみましょう。
様々な役割を担って日々頑張っている自分のために、罪悪感を持つことなく気軽に相談できる相手や機関を日ごろから頭の片隅に置いておくことをおすすめします。
相談できる場所を探そう
◎学校、教育支援センター、フリースクール、病院、ソーシャルワーカーなど
保護者が子育てや学校との関係について悩んだときに、相談を受け付けてくれる機関は全国各地に設置されています。すぐに挙げられる例としては、
・お子さんの通う学校
・地域の役場、教育委員会や保健福祉課
・地域の病院
・民間のカウンセリング施設
・ソーシャルワーカー
・フリースクール
・地域の教育支援センター
などが挙げられますが、「どんな場合にはどこに相談すればよいのか?」が初めての方にはわかりにくい場合もあります。今後、当サイトにて各施設の特徴についてもご紹介してゆきますので、ご参考になさってください。
◎鳥取県特有の認定の制度とは?
全国の自治体で、不登校児童生徒へのサポート体制の拡充が進んでいます。
鳥取県では「教育委員会認可制度」を導入し、フリースクールを正式な「学びの場」として認めて県の教育行政が積極的に関与・支援しています。また、フリースクールに通う児童生徒のための補助金制度により、授業料や交通費の一部を県が負担しています。
県が認定するフリースクールに通った日は、「出席扱い」として学校に行ったとみなされるのも、認定制度の特徴です。
家族だけで抱え込まないために
◎保護者同士の交流やオンラインコミュニティ
クラスにひとり以上は不登校の生徒がいると言われる現代、不登校の児童生徒を見つめる社会の視線も変わってきています。全国各地で不登校児童生徒を持つ「親の会」が立ち上げられたり、オンラインのコミュニティで保護者同士の学習会が開催されていたりという例もあります。
不登校を特別なことやネガティブなことととらえずに、そのようなコミュニティに参加してみることで新しい視点で状況をとらえることができるかもしれません。
◎公的・民間の相談窓口
いきなりオンラインコミュニティや「親の会」に参加するのはハードルが高い…と感じる方は、公的機関や民間施設の無料相談会を利用されることをおすすめします。
鳥取市では、教育委員会に不登校相談窓口が設けられているほか、24時間子どもSOSダイヤルや不登校電話相談も受け付けています。
また、メールで相談を受け付けている相談機関もあります。
・鳥取県教育委員会 不登校相談専用電話
0857-31-3956(月~金 8時30分-17時15分、年末年始・祝日は除く)
・鳥取県教育相談センター いじめ110番
0858-28-8718(24時間対応)
・鳥取県 いじめ相談専用メール ijime@g.torikyo.ed.jp
これ以外の相談窓口も、当サイトにてご紹介してゆきますので参考になさってください。
子どもの力を信じてみよう
◎学校復帰にこだわらない
「学校に行きたくない」という子どもは、ひと昔前であれば悪い子、意気地のない子と言われていたかもしれません。
しかし冒頭でも述べたように、平成28年に「教育機会確保法(通称)」が公布され、令和元年には「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知が国から発行されました。
これを受けて、不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自分でどうしたいかを考えることが大切だという理解が深まりました。
さらに学校側でも、「不登校児童生徒への支援においては要因・背景を的確に把握し、児童生徒理解に基づいたきめ細かな支援を行うことが重要である」との考え方が全国的な共通認識となりつつあります。
「学校に戻らなくてはと、悩まなくてもいいですよ」と、国が言ってくれる時代になったのです。
◎学校以外の学びの選択肢
「学校に行かない」ことを選んだ児童生徒の選択肢は、10年前とは比較にならないほど増えています。
オンラインツールを利用して自宅で学習を進めたり、週に1,2回だけ学校に通ったり、近隣のフリースクールに通うことを選んだりと、現代の子ども達は学校以外の学びの選択肢には事欠かない、と言っても過言ではないかもしれません。
しっかり休んで心が元気になったお子様にとって、「学校に行かずに何をするか?」はきっと大きな関心事です。
大人がいろいろな情報を提示するのも効果的かもしれませんが、これを機会にお子さんの力を信頼し、親子で想像もしなかった未来の可能性についてイメージを膨らませてみるのも良いかもしれません。
まとめ
いかがでしたか? 不登校状態の児童生徒は増え続けていますが、その背景には・不登校児童生徒への理解が進んだこと
・学校以外の場所で学べる選択肢が増えたこと
・不登校児童生徒への支援体制が充実してきたこと
などの理由も考えられます。
子どもにとっての選択肢が多くなればなるほど、それぞれの選択肢について理解し、比較検討するための時間もかかります。
国も学校も、不登校児童生徒の皆さんに、「学校に戻る」ことを求めているわけではありません。あせらずにお子さん本人の気持ちを尊重しつつ、必要なサポートには遠慮なく頼りながら、ご本人とご家族にとって最善の道を見つけてみてください。


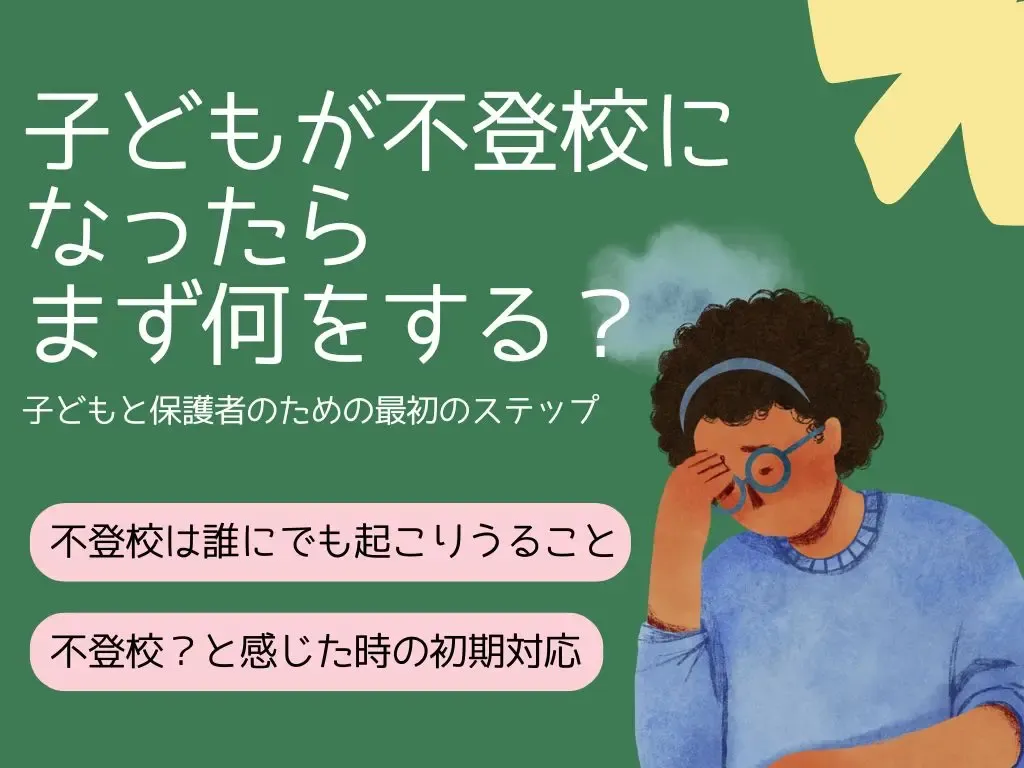
.webp)