◆教育現場の経験から支援の道へ。生徒支援・教育相談センターの役割
――まず、八木所長のこれまでのご経歴と、センターについて教えてください。
私はもともと、中学校教員です。学校で教育相談や不登校の担当として、悩みを抱える生徒たちと関わる機会が多くありました。
その中で、子どもたち一人ひとりに寄り添うことの重要性を強く感じてきました。その後、当センターでの勤務や再び中学校での勤務を経て、2年前から所長を務めています。
当センターは、2025年4月に「生徒支援・教育相談センター」という現在の名称になりましたが、以前は「いじめ・不登校総合対策センター」という名前で、2013年に設立されました。
当時は全国的にいじめや不登校が社会の大きな課題となっており、鳥取県でも学校が組織的に、そして一人ひとりの子どもを丁寧に見守りながら支援を進めていく必要がある、という考えのもと発足しました。
私たちのセンターの大きな特徴は、2つの大きな役割を担う担当部署が一体となって活動している点にあります。
一つは「生徒・学校支援担当」です。こちらは、主に学校や先生方を支援する部署です。各学校が抱える課題に対して、私たちが学校現場に入って一緒に考えたり、先生方への研修や助言を行ったりすることで、学校全体の支援体制を整えるお手伝いをしています。いわば、子どもたちを支える「環境」を整えるためのアプローチです。
もう一つは「教育相談担当」です。こちらは、支援を必要としている子どもたちや保護者の皆さんから、直接ご相談を受ける部署です。電話やメールで、不登校の悩みはもちろん、学校生活、友人関係、学習、子育てのことまで、幅広くご相談いただけます。
このように、学校という組織へのアプローチと、子どもや保護者という個人への直接的なアプローチ、この両輪を一つのセンターで担っているのが、私たちの特徴です。
.webp)
所長の八木さん。お忙しい中朗らかに迎えてくださいました。
◆増加する不登校。「多様な選択肢」が子どもたちの安心につながる
――全国と同様に、鳥取県でも不登校は増加傾向にあると伺いました。現状をどのように捉えていますか?
はい、鳥取県でも不登校の児童生徒数は増えています。しかし、私たちはこの状況を単に数字として捉えるのではなく、「子どもたちが発しているSOSの表れ」だと考えています。だからこそ、私たち大人がすべきことは、まず子ども一人ひとりの心に深く寄り添い、その子の中にすでにある「答え」を一緒に見つけ出し、引き出してあげることだと思うのです。
時にはじっと見守り、時には励まし、応援する。学校の先生、保護者の皆さん、そして私たちのような支援機関、さらには地域社会全体が一体となって、子どもたちを支えていくことが何よりも大切だと感じています。
――子どもたちを支える上で、鳥取県が先進的だと言われる「多様な学びの選択肢」について教えてください。
私が中学校の現場にいた頃から強く感じていたことですが、「教室」という空間がどうしても苦しい子にとって、「教室以外の居場所」があることは、計り知れないほどの安心感につながります。
「教室には行けなくても、学校の中に自分の居場所がある」。それは、保健室や相談室かもしれません。それだけで、子どもは「自分は受け入れられている」と感じることができるのです。
その考え方は、学校の外にも広がっています。鳥取県では、学校という枠組みだけでなく、様々な学びの場が用意されています。
- 教育支援センター:市町村が設置し、小中学生が通える学びの場・安心できる居場所です。
- フリースクール:民間の団体が運営する、自由な学びの場です。
- ICTを活用した在宅学習:自宅にいながら、オンラインで学習を進める方法です。
大切なのは、「この方法が一番良い」と決めつけるのではなく、子ども自身が「これが自分に合っている」と思えるものを、主体的に選べる環境があることです。
ある子にとっては少人数で過ごせる場所が安心できるかもしれませんし、別の子にとっては自宅から少し離れた場所の方が通いやすいかもしれません。子ども一人ひとり、安心できる形は違います。その子に合った選択肢を複数提示できる支援体制こそが、これからの時代に求められていると考えています。
.webp)
◆保護者の悩みに寄り添う相談窓口。子育ての不安も「まずはご相談を」
――センターに寄せられる相談の多くは、保護者の方からだと伺いました。
はい、電話やメールでのご相談は、そのほとんどが保護者の皆さんからです。ご相談内容は多岐にわたりますが、最も多いのは不登校に関するお悩みです。そこから派生して、学校での対人関係や学習のこと、さらには家庭生活や子育てそのものに関するご相談へと広がっていくケースも少なくありません。
例えば、「子どもが学校を休みがちで…」というご相談の背景に、ご家庭の様子や保護者さんご自身の育児に対する不安が隠れていることもあります。一つの悩みは、様々な要因と複雑に絡み合っているのです。私たちは、そうした背景も含めてじっくりお話を伺い、一つひとつ丁寧に紐解いていくことを心がけています。
――相談後は、具体的にどのようなサポートをされるのでしょうか?
相談員は、まず相談者さんに寄り添い、話をしっかりと聴かせていただきます。そのやり取りの中で、相談者さんの不安が軽減したり、前向きな気持ちの変化が見られたりするようになります。
また、相談者の方のご希望を第一に、柔軟な対応もしています。例えば、「センターから学校へ、この状況を伝えてほしい」というご依頼があれば、そのような動きを取ることもあります。逆に、こちらから「担任の先生に、まずはお話しされてみてはいかがですか?」あるいは「担任の先生が難しければ、学年の先生や教頭先生など、話しやすい先生に相談してみるのも一つの方法ですよ」と、ご自身で次の一歩を踏み出すための後押しをすることもあります。不安になられたら、また相談してくださっていいことも伝えます。
私たちの相談窓口は、毎日複数件のご相談をいただいています。子育ては本当に大変なことですし、広範囲にわたる悩みを抱えて当然です。不登校のことだけでなく、ご家庭のこと、子育てのこと、どんな些細なことでも構いません。「こんなこと相談していいのかな?」と思わずに、ぜひ一度、ご相談いただければと思います。
ただ、私たちの大きな課題として、「こうした相談窓口の存在が、本当に必要としている方に十分に知られていないのではないか」という現実があります。学校で配布物をお渡ししても、学校に来られていないお子さんや保護者の方には届きにくい。どうすればこの情報を届けられるか、私たちも日々模索しています。この記事を読んでくださっていること自体が、私たちにとって大きな一歩です。
◆高校生世代の「社会的自立」を応援するハートルフルスペース
――センターの取り組みの中でも、特にユニークなのが「ハートルフルスペース」だと伺いました。
はい、「ハートルフルスペース」は、県教育委員会が運営する中学校卒業後の高校生年代の若者を対象とした教育支援センターです。
鳥取県では、小中学生を対象とした教育支援センターは各市町村が運営し、県は高校生年代以上を対象とする、という役割分担をしています。
対象となるのは、例えば、
- 高校に進学したものの、休みがちになっている生徒さん
- 高校には進学せず、これからの道を模索している若者
- 定時制や通信制高校に在籍し、日中の居場所や活動の場を求めている生徒さん
など、様々な背景を持つ若者たちです。
活動内容は、調理実習やボウリング、陶芸、美術館鑑賞といった体験活動から、学習支援、さらにはカウンセラー・ソーシャルワーカーによる専門的な支援まで多岐にわたります。みんなで一緒に活動する日もあれば、それぞれの目標に向かって静かに学習等に取り組む時間もあります。
私たちが「ハートルフルスペース」で目指しているのは、若者一人ひとりの「社会的自立」を応援することです。その形は、大学や専門学校への進学かもしれないし、就職かもしれません。あるいは、まずは安心して過ごせる居場所を見つけ、家から一歩踏み出すことかもしれません。目標は一人ひとり違っています。私たちは、彼らが自分自身の力で未来を切り拓いていくための、温かい伴走者でありたいと思っています。
――支援の現場で、やりがいを感じるのはどんな瞬間ですか?
私たちは、様々な専門性を持つ職員がチームとなって、相談者さんや利用者さん一人ひとりに向き合っています。ある職員は積極的に励まし、ある職員はそっと見守る。ある職員は温かい言葉をかけ、またある職員はぐっと背中を押してあげる。こうした多様な関わり合いの中で、相談者さん・利用者さんが少しずつ心を開いたり、自分らしい姿を見せてくれたりすることが、私たちにとって何よりの喜びです。
難しいことですが、相談者さん・利用者さんの小さな変化や成長を見守ることができるのは、この仕事の大きなやりがいです。なにより、このセンターに来てくれる、それだけで本当に嬉しいです。
◆悩んでいる子どもたち、そして保護者の皆さんへ
――最後に、今まさに悩んでいる子どもたち、そして保護者の皆さんへメッセージをお願いします。
まず、子どもたちに伝えたいのは「あなたは一人ひとり、みんないいところがあって、かけがえのない大切な存在なんだよ」ということです。
そして、保護者の皆さん。子育ての中で困難に直面し、思い悩むのは当然のことです。どうか、一人で抱え込まないでください。
学校の先生、私たちのような相談機関、教育支援センター、フリースクール、あるいは地域の親の会など、皆さんの周りには相談できる場所がたくさんあります。まずは、話しやすいと感じる場所に、皆さんの心の内を言葉にして伝えてみてください。
私たちは、「子どもの行動の答えは、その子ども自身の心の中にある」と考えています。だからこそ、まずはお子さんが心から安心できる環境を作ってあげることが大切です。そして、そのためには、保護者の皆さん自身の心が安定していることが不可決です。保護者の皆さんの安心は、必ずお子さんに伝わります。
お子さんの力を信じて、その子の中にある答えを一緒に探してあげてください。時には我慢強く待ち、じっと見守ることも必要かもしれません。
私たちも、皆さんと一緒に、子どもたちを応援していきたいと思っています。いつでも、皆さんからのご相談をお待ちしています。
――八木所長、本日は温かいお話を本当にありがとうございました。
.webp)
八木所長(右)とつなかん代表明石
取材を終えて、八木所長の言葉一つひとつから、子どもたちへの深い愛情と、支援への揺るぎない信念が伝わってきました。
もしあなたが今、子どもの不登校で悩んでいるのなら、どうか一人でその重荷を背負わないでください。鳥取県には、あなたの心に寄り添い、共に歩んでくれる人たちがいます。その一歩を踏み出す勇気が、お子さんとあなた自身の未来を、きっと明るく照らしてくれるはずです。
【相談窓口のご案内】
- 鳥取県生徒支援・教育相談センター
- 不登校相談電話:0857-31-3956(平日8時30分~17時15分)
お気軽にご相談ください。 - メール:soudan@g.torikyo.ed.jp
不登校に限らず、教育に関する様々な相談を受け付けています。 - 生徒支援・教育相談センター情報(ドキュメント)
- 不登校相談電話:0857-31-3956(平日8時30分~17時15分)
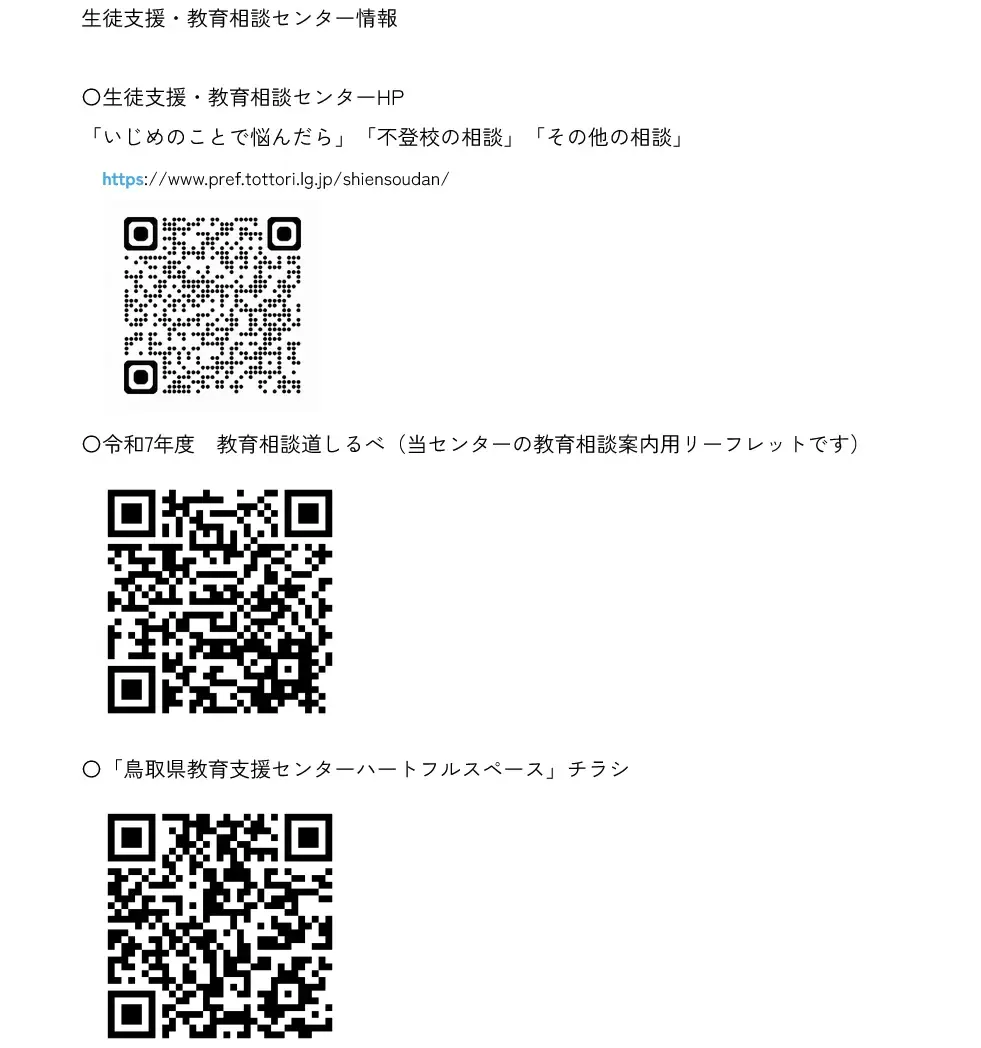
(※連絡先等の詳細は、生徒支援・教育相談センターのホームページをご確認ください)


-1.webp)
.webp)